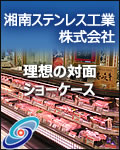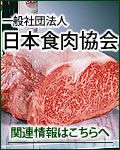| |
事務局からのお知らせ最新Topics
生レバーの流通規制について2012年04月02日
平成24年4月2日 県肉連会長各位 全国食肉事業協同組合連合会 生レバーの流通規制について 前略、日頃は全肉連の事業推進にご協力頂き厚く御礼申し挙げます。 既に、マスコミ等で報道されたとおり、3月30日に厚生労働省「食中毒・乳肉水産食品合同部会」が開催されました。 * 生肉・生レバーについては、枝肉・内臓検査により合格した物のみ流通させるのが食肉検査場を管轄している厚労省の役目 * 生レバーを規制すれば、食肉販売業者・内臓業者のみでなく、生産者が痛手になる。 * 以上の他、次ページの「生食・生レバーを衛生的に提供することについて」に沿った意見陳述をしました。 しかし、部会の最後に別添の「牛肝臓の取り扱いについて(案)」が配布され、マスコミの記事になった次第です。 今後、牛レバー、生肉の各種実験を継続してゆくとともに、広く食肉業界・飲食業界とスクラムを組んで、差し止請求等、法的な手段も含め取り組んで行くことと致します。 生食・生レバーを衛生的に提供することについて
1. 客観的・科学的な情報の提供を再度お願いしたい 客観的・科学的なデータの提出を、前回の部会でお願いしているが、示されていない。 ① 「通常では、発見できないので、腸管出血性大腸菌(0・157)が発生し易い、農場・と畜場を選んで、取りまとめた」 データを示されたままです。 ② 取りまとめられた実態調査は、「腸管出血性大腸菌の保菌率が高いことが推定される個体を選定する」なかで行われており、客観的なリスク評価が出来ないのではないでしょうか。 ③ 私どもとしても、大学の研究室や食肉試験機関と、実験を実施中でありますが、と畜場と離れているため、細菌検査1つとっても、時間や費用がかかります。 厚生労働省では、と畜場の食肉検査場を活用すれば、客観的データ等の収集は容易に行えるのであるから、再度、データを取りなおし、収集をお願いしたい。 2. と畜場での汚染防止策 *先だって、厚木にある民間の食肉センターを部会長と一部委員には、見学
頂きました。 *これ等は、食肉検査員と畜場の管理者・作業者が、官民一体になって取り組めば、防止出来る事柄であると思います。 ① と畜場での細菌汚染の原因 ア、腹腔から内臓を取り出す際の細菌汚染。 * 食道・肛門結札が十分でなく、腸内等の内容物が内臓に触れる。 * 食道・直腸の一部が損傷し、腸内等の内容物が内臓に触れる イ、内臓処理・検査過程での細菌汚染。 * 内臓の赤物(レバー、ハツ等)と白物(胃・腸等)を分離する際にレバー表面を、血液(門脈等)等が汚染する。 * 内臓(レバー)検査の際、胆嚢を切開することにより、内容液(胆汁等)がレバー表面を汚染する。 ② 細菌汚染防止の対策 * 今は、枝肉と同様に、洗浄や一部割除による対応にしているがこれ等の内臓は、全て生食用の対象から除外する方策を考える。/
* 門脈等の結札をしてから、赤物、白物の分離を図る * 胆嚢・レバーの検査方法を改める。 ③ 食肉センター作業員、市町村の食肉衛生検査員の協力により、上記の事を実行することになる。 ④ 但し、生きたレバーの細胞の中に、病原微生物はいない前提で、以上を考えています。 *生理現象から、生きている間は、肝臓の細胞の中に腸管出血性大腸菌がいることはなく、と畜後に、胆嚢等から腸管出血性大腸菌その他の病原菌が、胆汁を含め、レバーの細胞組織の中に入り増殖する。 *もしこれと違って、生きた牛のレバー細胞の中にいるとのことであるならば、そのデータを出して頂きたい。 3. 私どもの実験の内容と、その結果について ① 大腸菌の浸透試験と畜後の拡散防止試験 * 大腸菌を胆嚢に注入、レバーの組織の何処まで浸透していくか。 *と畜後、出来る限り早く、胆嚢を結札し、その場合の菌の分布に変化が見た場合は、胆のうを結札した場合と比べ細菌の発生が抑えられた。 ② と畜後のレバー洗浄試験 * 次亜塩素酸ソーダ等によって洗浄することにより、生食に耐え得る衛生状態に成るか否かの細菌増殖試験では、レバー表面の細菌汚染は洗浄する事でクリア―出来ることが解った。 * 今後は、血管・胆管を洗浄する事によって、細菌の組織内への汚染が防止できるか否かの実験をして行くこととなる。 * 今回の実験は、検体数が少ないので、継続して実験データを取り揃えることと致したい。 ③ 生食レバー提供時の衛生検査 * 生肉・生レバー用、柵(ブロック)取り部分の限定 牛レバーについては、通常の商品提供で行っている、胆管より離れた部分に限定して、生食用の柵取りを行い、その商品の細菌検査試験等を行ってゆく。 4. 食肉業界の取り組み ① 生食のリスクの情報提供 *店頭でのポスター・リーフレット等の表示と情報提供を行っている。 ② 衛生的な処理・加工の徹底 ア、 枝肉・部分肉・内臓の衛生的な加工をさらに、徹底する。 部分肉のリンパ・血管、レバーの胆管・血管の丁寧な除去を行う特にレバーについて、洗浄の徹底 胆のう除去後の胆管・血管の洗浄を徹底する(殺菌作用のある機能水等の利用を図る) イ、 加工手引書(ガイドライン)の作成(平成24年度中) ○ ガイドラインの作成 ○ 生肉・生レバー用、柵(ブロック)取り部分の限定生肉の部分肉からの柵取りや、牛レバーについては ○ 生食用の期限設定
③ 資格認定の設定(今後1~2年を目標に) ア、ガイドライン等を教本として、定期的に衛生加工講習会を開催する。 厚生労働省、市町村保健所、食肉検査所等に協力を仰ぎ、食肉業界で「生食加工資格試験」制度を創設して、資格認定に合格した者のみが、生食の加工に携わることとする。 5. 生食特区の創設(今後の検討事項) 1定のエリア(県・市・町等)を定め申請させ、認める。 一定エリアを管轄する保健所、と畜現場での食肉検査所に協力を仰ぎ、と畜場での処理、副生物組合・内臓卸業者での加工、焼肉店店舗など、一定エリアでは、生肉・生レバーが衛生的に供給加工され、好みで(本人のリスク)で、いつでも飲食出来る特区を創設する。 |