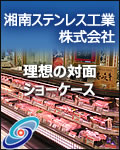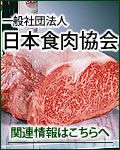平成24年5月10日
食肉関係団体
道府県食肉事業協同組合(連合会)
全国食肉事業協同組合連合会
会長 福岡 伊三夫
牛生レバーの規制に反対する要望書の提出と
署名活動のお願い
前略、
日頃は全肉連の諸活動に、ご指導、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
さて、マスコミなどでもご存知のとおり、厚生労働省では、牛の生レバー提供禁仕の方向で(厚生労働省のホ-ムページで、「牛レバーは30分以上加熱すること・・」のパブリックコメントを現在求めています)法律の変更がされようとしております。
昨年10月の、牛肉の生食についての基準改正に続くもので、この先、他の食肉の規制も強化され、このまま看過するわけにはゆかない状況です。
そこで、別紙の「要望書」を厚生労働大臣に提出することとします。
(参考のために「要望書の解説書」もお送りします。)
また、食肉の各団体、各企業、店舗はもとより、消費者に賛同を得ることが必要と考え、別添のレバーの生食提供規制の反対署名活動をお願い致したく、ご案内申し上げます。
草々
≪資料≫
(1)〈要望書〉(添付/5月9日要望書)
(2)〈要望書の解説〉(添付/5月15日厚生労働大臣要望、解説書)
(3)〈牛レバーの生食(なましょく)規制に、反対する署名〉
※署名用紙(PDF)をプリントアウトしご記入ください。
(添付/5月10日署名活動)
厚生労働大臣
小宮山洋子殿
要望書
■ 牛レバーの生食規制には、あくまで反対します。
1. 国民が自ら摂る食事の、その材料や調理方法については、基本的に自己の責任において自由に行うことが基本であり、法律で規制すべきでない。
2. 日本には刺身、生卵、生牡蠣など、永年にわたり生での食習慣が根付いている。 ある程度のリスクを理解しつつも、生レバーを食べたい消費者も多くいる。 もし、新たな規制を導入するには、それ相当の消費者の要望や、リスク評価の他、規制導入による関係業界の影響等、広範な検討をして決定すべき。
3. リスク評価は、偏りのない試料で行なうべきなのに、2次汚染の疑いのある、一部のと畜場の検査等を集め、規制をするために都合のよい試料を示し、これを根拠に生レバーの提供を禁止するのは許し難い。
4. と畜場の処理方法を改善することにより、また殺菌効果のある新たな処理方法の導入により、リスクの低減をはかれる。
これでも許されないなら、腸管出血性大腸菌(0・157等)の有無を個体毎に検査し、リスクの無いものを選別し、流通する事が可能である。
平成24年5月15日
全国食肉事業協同組合連合会
会長 福岡 伊三夫
全国食肉生活衛生同業組合連合会
会長 肥後 辰彦
全国食肉業務用卸協同組合連合会
会長 山下 久
社団法人 日本畜産副産物協会
会長 本山 逸郎
事業協同組合 全国焼肉協会
会長 新井 泰道
社団法人日本食肉協会
会長 神崎 吉章
<要望書の解説書>
牛肉・牛レバーの生食提供規制に断固反対します
■ 生食・さしみの文化を守ろう
・厚生労働省は、昨年10月、牛生食の厳しい基準を作りました。
現在、本年6月に向けて、牛レバーの生食を禁止するために、準備を着々進めています。
・これ等を審議した部会では、牛レバーと同様にこの先「牛の胃袋」や「蒸し鶏」についても、規制する話が出ています。
・このままで行くと、「生卵の飲食は危険だから提供を禁止する」ことにもなりかねません。
・同じ論理で行けば、最も食中毒の多く発生している魚介類のさしみも食べられなくなります。
・・もっともこれは国民の反発も多くあり、手を付けないかもしれませんが
■ 生で食品を食べるのはリスクがあります、このリスクをゼロに近づける努力を、行政と業界がすべきことではありませんか。
・毎年3万件を超える、食中毒が発生しています。
その多くは、魚介類と食肉が原因です。
・私ども食肉の加工・卸・小売・飲食の業界では、食中毒を起こせば営業が停止され、店や、企業の死活問題です。 従って、日々衛生に十分気を付けて、食肉の、処理・加工・提供を行っています。
・しかし、食品は、無菌ではありません。
ましてや、生で食べるものすべて、さしみにしても、野菜サラダにしても、食品表面には雑菌があることを前提にして、洗浄を徹底し、衛生的調理に努めることになります。
・食肉業界では、「肉は生で食べるのはリスクが有ります」「十分火を通して召し上がって頂きたい」旨の、情報を提供しながら、食肉を店頭販売しています。
・こうした環境のなかであっても、「牛のさしみ」は和食料理店やフレンチレストランで提供され、「牛生レバー」は焼肉店の定番になっていますし、家庭でユッケを食べる方も多くいます。
このように提供され、料理された食品を、個人の判断と責任で飲食するものに、食品衛生法の規格・基準で取り締まるのは如何なものでしょう。
■ 間違いの多い、守れない基準を作るべきでない
・昨年作られた牛生肉の基準では 「材料は枝肉から切り出して~」
「表面から1㎝のところを60℃で2分間以上加熱すること」としました。
・枝肉から切り出して、牛刺し、牛ユッケを作る人はいません。枝肉から部分肉を作り、これが小売店、飲食店に流通して、そこから、牛刺し、牛ユッケを作ります。版画を作るのに、丸太から切り出しなさい、と言うに等しい事です。 間違った基準は訂正すべきです。
・今食肉業界では「表面から1㎝のところを60℃で2分間加熱」する実験を専門家にお願いしていますが、容易ではありません。
厚生労働省も、机上で考えただけのマニュアルを押し付けるのでなく、
実験してみては如何でしょうか。
・今回も「牛の肝臓を加工調理する場合は、63℃で30分間加熱調理するか、同等の加熱殺菌をしなければならない」とのこと。
法律で調理の時間まで規制するのは如何なものでしょうか。
・30分加熱調理とは、牛レバー全体を調理する事を考えているのでしょうか。 通常使う、短冊や切り身のレバーを30分も加熱したら、佃煮です。
・5分内外で調理し、提供されている中華の「レバー・ニラ炒め」を飲食店で提供してはいけないと言うことになります。
■ 厚生労働省は、科学的な根拠を示さずに、食肉の生食を禁止する法律制定を急いではいけない。
・食べ物の流通を規制するためのリスク管理の方法を決めるには、データに基づいたリスク評価と、どの程度のリスクを社会が受け入れるかを見極め得るリスクコミニケーションしていかねばなりません。
ところが厚労省の部会で示された調査結果は、厚労省からの指示文書にあるように「腸管出血性大腸菌の保菌率が高いことが推定される個体を選定する」なかで行われており、取りまとめた責任者の発言にあるように「通常では、発見できないので、腸管出血性大腸菌(0・157)が発生し易い、と畜場等を選んで、取りまとめた」ことのみを根拠にしていること。
また、牛肝臓の表面に0・157が付着しているような(これは胆汁液もしくは腸内物に汚染されている)検体を使って、肝臓の組織内に腸管出血性大腸菌(0・157)が存在したとするのは、おかしいと思います。
これでは、客観的なリスク評価が出来ないのではないでしょうか。
・厚生労働省では、と畜場の食肉検査場を活用すれば、客観的データ等の収集は容易に行えます。
再度、データを取りなおし、客観的なリスクを示すべきです。
私どもとしても、大学の研究室や食肉試験機関と、実験を実施中であり
ますが、と畜場と離れているため、細菌検査1つとっても、時間や費用
がかかります。
厚生労働省が、再度検証をしないならば、私どもの検証結果が出てから
基準をつくるべきです。
■ 生で食べられるよう、衛生的な処理の改善をして来ました。
・昨年春、焼肉チェーンで腸管出血性大腸菌による食中毒事件が発生しました。 子供さん、お年寄りが亡くなられた痛ましい事故でした。
・ 原因ははっきりしています。
焼肉チェーン店へ、ユッケの材料を卸す加工業者も、焼肉チェーンでも、それまでに厚生労働省が通知した、「肉塊のトリミング」をしていなかったのです。
卸業者、焼肉店の何れかがトリミングしていれば、また、旧来の基準を守るよう、管轄の保健所が衛生指導していれば、起きなかった事件です。
・腸管出血性大腸菌(0・157)の食中毒事件は、今から17年前(1996年)にも起き、死亡事件を起こしています。
いわゆる、カイワレダイコン騒動です。
これを機に、厚生労働省は、「と畜場法」を改正し、「食道と肛門の結札」「1頭毎にナイフを変え、83℃の熱湯で消毒する」等の決まりを制定しました。
・私ども食肉業界では、全国のと畜場で、費用をかけて熱湯消毒の装置を整備し、食道・肛門結札の作業を行う等をして、これに対応しました。
これ等によって、牛肉や牛レバーは、生で食べても良い衛生基準となったはずです。
・生肉の原料になる枝肉も、レバーを含んだ内臓も、1頭ずつ厚労省管轄の食肉検査員が検査し、私どもはその検査料を支払っています。
衛生的な牛肉・牛レバーを流通させるため監視・検査するのは、もともと、厚労省の役目です。
■ 衛生的なレバーの提供は出来ます。
・腸管出血性大腸菌は、牛の腸管内に存在することは以前より分っている事ですし、「牛の肝臓の組織に存在した」との結果ですから、これを前提に対応を考えることとなります。
・肝臓の組織の中とは、「肝細胞の中まで入っているのですか」それとも「肝臓内の胆管や血管に有るのですか」との質問に、厚労省は答えていません。
・しかし、と畜以前から、生きた肝細胞の生理現象(肝臓で胆汁をつくり、胆嚢の方に流れる)から、生きている間は、肝臓の細胞の中に腸管出血性大腸菌がいることはない。
もし、細胞内に存在すれば、何らかの病変を肝臓検査で発見出来ます。
・肝臓の組織から腸管出血性大腸菌の存在が確認できたのは、「と畜後に胆嚢等から腸管出血性大腸菌、その他の病原菌が、胆汁を含め、レバーの細胞組織の中に入り増殖したもの。」というのが、獣医学の常識です。
今回の調査でも、生きた牛のレバー細胞の中にいるとの、データは出さ
れていません。
・従って、と畜後に出来るだけ早く、肝臓を取り出して、肝臓を検査した直後に胆嚢をレバーより切り離し、直ちに胆管や血管を洗浄する。
徹底した洗浄をすることで、病原微生物の存在は除去できるはずですし
私どもの洗浄実験では、それを可能とする結果が得られています。
・洗浄の他にも、腸管出血性大腸菌(0・157)や病原微生物の殺菌をすることが出来る情報が寄せられています。 例えば、放射線照射による殺菌は海外で利用され、有力な手段の1つです。
許されれば、この実験もして参りたいと思います。
また、生食用に使用される牛レバーは、胆管や血管から離れた部分に限定して、生食用柵取りを行っていますのでより安全に提供できます。
■ 「牛レバーを安全に生食するための予防対策が見いだせない」
だから、生食を禁止すると言っています。本当ですか。
・厚生労働省の示したデータでも、腸管出血性大腸菌が存在する、レバーはごく一部です。 海外のデータでは、0.4%とのことです。
・腸内容物(糞便)と、胆汁液をPCRで検査をして、腸管出血性大腸菌(0・157)の存在しないレバーのみを流通させることも可能ではありませんか。
・これ等の検査は、厚生労働省管轄の食肉検査場で行えますから、厚労省がその気になれば出来ることです。
・全国で一斉となれば、人手を含む予算多くかかり、直ぐには出来ないことです。
・そこで、当面は私どもの提案してきた、特区構想です。
特定のと畜場・食肉検査場と流通業者が一体となって、検査し、徹底した洗浄をした、特定のレバーを流通させる。
これを、一定のエリアを設定し、専門の講習を受講した調理士によって飲食提供をする。
・もし、厚生労働省がしなければ、食肉流通業界と焼肉業界で取り組みます。
レバーの生食提供を法律で禁止する事だけは、してはならないことです。
(予定団体)
全国食肉事業協同組合連合会
会長 福岡 伊三夫
全国食肉生活衛生同業組合連合会
会長 肥後 辰彦
全国食肉業務用卸協同組合連合会
会長 山下 久
社団法人 日本畜産副産物協会
会長 本山 逸郎
事業協同組合 全国焼肉協会
会長 新井 泰道
社団法人日本食肉協会
会長 神崎 吉章